国民健康保険税の制度
国民健康保険は、0~74歳までの医療保険です。個人ごとではなく、世帯ごとに課税されます。
保険税額の計算方法
1年間の保険税額は、次の表の1~3の組み合わせで計算した金額をご負担いただいています。
|
区分 |
算出内容 |
医療 |
後期高齢 |
介護 [40~64歳該当] |
|---|---|---|---|---|
|
1.所得割額 |
前年の所得金額-430,000×右の率 |
6.1% |
2.5% |
2.3% |
|
2.均等割額 |
1人 / 加入額 |
20,500円 |
8,100円 |
8,700円 |
|
3.平等割額 |
1世帯 |
21,300円 |
7,200円 |
7,000円 |
|
賦課 限度額 |
各項目の最大課税額です。 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
- 40~64歳の方は、医療分と支援金分と介護分の3つ全ての合算額が税額となります。
- 0~39歳の方、65~74歳までの方は医療分と支援金分の2つの合算額が税額となります。
軽減制度
以下に該当する世帯には、保険税の軽減があります。
1.前年の所得が下記の一定額以下となる世帯
加入者全員の所得の合計額が、下記により計算した、所得金額以下の世帯は、均等割合と平等割合が軽減されます。
ただし、世帯内に未申告の方が居ると、軽減措置は、適用外となります。ご注意下さい。
届け出不要です。
| 軽減率 | 計算方法 |
| 7割 | 基礎控除額430,000+[(給与所得者数ー1)×100,000]以下の世帯 |
| 5割 | 基礎控除額430,000円+[(給与所得者数ー1)×100,000]+(305,000×加入者人数)以下の世帯 |
| 2割 | 基礎控除額430,000+[(給与所得者数ー1)×100,000]+(560,000×加入者人数)以下の世帯 |
2.未就学児の均等割合を5割軽減
小学校入学前の児童は、均等割合が半額となります。
届け出不要です。
3.妊娠・出産時の所得割合・均等割合の減免
出産前後の期間(単胎の方は出産予定月の前月から4カ月間、多胎の方は出産予定月の3カ月前から6カ月間)の対象者の国民健康保険税から、所得割と均等割を減免することができます。
届け出が必要です。
出産予定日の6カ月前から届け出を受け付けています。出産後の届け出も可能です。
産前産後の保険料金免除 詳細説明(PDFファイル:141.4KB)
4.非自発的失業者(リストラ等での離職)の軽減
倒産や解雇といった理由で離職を余儀なくされた方の税負担を軽減する制度があります。
届け出が必要です。
ハローワークにて雇用保険受給資格者証を受け取り、つぎに該当する方が対象です。
対象者
- 雇用保険の特定受給者(例 倒産、解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける65歳未満の方。
軽減内容
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなします。(例:前年100万円だった方は、30万円として税額を計算します。)
ただし、1世帯内の申請者以外の加入者の所得は軽減されません。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
対象となる理由コード
雇用保険受給資格者証の「12離職理由」欄(旧様式「13.離職年月日 理由」)の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば対象となります。
- 特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者:23、33、34
該当される方は、雇用保険受給資格者証をご持参のうえ申請をお願いします。
国民健康保険税減免申請書(非自発的離職者用) (PDFファイル: 37.5KB)
5.後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減
75歳になると、後期高齢者医療保険に移行加入となります。
その世帯に国民健康保険加入者がまだ居た場合、後期高齢者医療保険と併せて、2つの保険の料金が発生することになります。この際に、負担額が急激に増えることがないように、国民健康保険税の、一定期間の軽減の経過措置がされます。
国民健康保険に残る方がいる世帯
引き続き国民健康保険に加入する方がいる世帯は、税額を軽減します。
届け出不要です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 低所得世帯への軽減 | 従来、軽減を受けていた世帯では、世帯構成や所得が変わらなければ、従前と同様の軽減が継続されます。 |
|
平等割合[1世帯]の軽減 |
加入者が1人だけになる世帯[特定世帯といいます。]は、5年間は、平等割が50%・6年目から8年目は75%になります。 |
扶養家族である方が、新たに国民健康保険に加入する場合
75歳以上の方が、会社の被用者健康保険から後期高齢者医療保険へ移行することで、その被扶養者だった65~75歳未満の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入せざる得なくなった場合、税額を軽減します。
届け出が必要です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 国民健康保険に加入となった旧被扶養者 |
1.所得割合・資産割合は免除 2.均等割が、最長2年間半額 3.旧被扶養者のみの世帯は、平等割合も最長2年間、半額になります。 |
保険税の納め方
保険税の納税義務者は、世帯主です。
年額を6月から翌年3月までの10回に分割して納めます。(2期以降の納入金額は千円単位とし端数は1期分にまとめます。)年度途中で国保に加入・脱退した場合は月割りで計算し納付いただきます。
現金納付の方
各期に納付書を送付します。
次のいずれかの窓口で納付してください。
- コンビニエンスストア
- 銀行、信用金庫、農業協同組合 金融機関
- 飯島町役場 会計課
口座振替の方
納税義務者が届け出た金融機関の普通(総合)口座から、納期ごとに納付する方法です。各月の納期限日に振替させていただきます。
- 口座振替による納付を希望されるときは、役場税務係窓口又は、町内の金融機関(ゆうちょ銀行は除きます。)から口座振替の申込書を受取り、必要事項を記載して、金融機関に提出してください。
- 申出のあった翌月分から口座振替による納付が行われます。
特別徴収(年金天引き)の方
平成20年10月から年金からの特別徴収(年金天引き)がスタートしました。
対象となるは、国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主であり、年額18万円以上の年金を受給している方で介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方です。
介護保険料が特別徴収されていない方、またその年度に75歳になる世帯主の方は特別徴収になりません。
対象者
次の要件を全て満たす納税義務者は、特別徴収になります。
- 課税する年度の4月1日現在、国民健康保険税の納税義務者が公的年金を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主
- 国民健康保険に加入している世帯主及び世帯員全員が65歳以上75歳未満であること
- 公的年金の年額が18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以下である人
仮徴収と本徴収
2月に特別徴収で国民健康保険税を納付し、4月以降も特別徴収により納付する方の期別の税額は、2月の金額を「仮徴収額」として4月、6月、8月の年金から納付します。6月に国民健康保険税の年額が決定します。4月から8月までに納めた額を差し引いた額を10月、12月、翌年2月の年金から納付します。
新たに特別徴収になる方は、10月から特別徴収を開始します。この場合、6月から9月までは「普通徴収」になります。
年金からの特別徴収から口座振替への支払い方法の変更について
国保税について、平成20年10月より年金からお支払いいただく予定となっている方のうち、以下の1.及び2.のいずれの要件も満たす方は住民税務課税務係の窓口へ申請いただくことにより、国保税を口座振替によりお支払いいただくことができます。
- これまでに国保税を滞納することなく納めていただいている方
- これからの国保税を口座振替により納めていただける方
(注意)申出いただいた月日により年金天引きを中止できる月が違います。
保険税を滞納すると
特別な事情がなく保険税を滞納した場合には、やむを得ず次のような措置がとられます。
- 督促を受けたり延滞金が加算される場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 保険証を返却し、「被保険者資格証明書」が交付されます。(医療費はいったん全額自己負担になります)
- 保険給付の全部又は一部が差し止められます。
納付が困難なときは、住民税務課 税務係 窓口までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
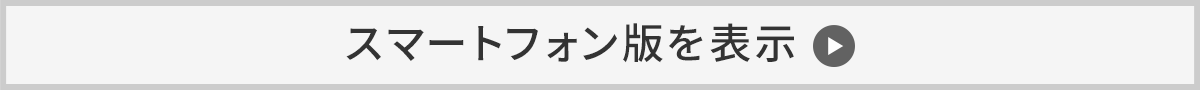












更新日:2025年06月16日