農業者年金制度
老後を安心して暮らすためには、若いうちからの備えが必要であり、年金への加入は欠かせません。
新しい年金制度は、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。
加入条件
農業者年金には、次の要件をすべて満たす方であれば、農地を持っていない農業者や家族従業者も加入できます。
- 国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者は除く)
- 年間60日以上農業に従事する方
- 20歳以上60歳未満の方
保険料の財政方式
保険料の財政方式は積立方式を採用しています。将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。
この収めた保険料総額とその運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。
加入者全員が65歳から受給できます。
(希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です)
保険料
毎月の保険料は、20,000円を基本に、最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められますので、経済的な状況や老後の設計などに応じていつでも見直すことができます。
年金の支給
農業者年金は80歳までの保証がついた終身年金です。仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳まで受け取れるはずであった農業者老齢年金が死亡一時金として遺族に支給されます。
税制面でのメリット
保険料は、全額(最高804,000円)社会保険料控除(所得税)の対象になります。
また、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象になります。
(個人年金の場合は、控除額の上限は50,000円です)
農業の担い手に対する政策支援(保険料の国庫補助)
認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす、意欲ある担い手は、政策支援の対象となり、一定の期間につき国の保険料助成を受けられます。
この助成を受けた保険料と運用益を基礎とする年金を特例付加年金といいます。
特例付加年金は、農地・採草放牧地及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなれば受給することができます。
保険料の補助対象者と国庫補助額
保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
1 認定農業者で青色申告者
- 国庫補助額 35歳未満 10,000円(5割)
- 国庫補助額 35歳以上 6,000円(3割)
2 認定就農者で青色申告者
- 国庫補助額 35歳未満 10,000円(5割)
- 国庫補助額 35歳以上 6,000円(3割)
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
- 国庫補助額 35歳未満 10,000円(5割)
- 国庫補助額 35歳以上 6,000円(3割)
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
- 国庫補助額 35歳未満 6,000円(3割)
- 国庫補助額 35歳以上 4,000円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者
国庫補助額 35歳未満 6,000円(3割)
農業老齢年金と特例付加年金

現況届について
現況届は、農業者年金を受給している方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業の再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。
(用紙は毎年5月下旬に農業者年金基金から各人へ送付されます)
農業者年金を受給されている方は、本人(本人の署名が困難な場合は代理人の署名等)が署名の上、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。提出がないと年金の支払いが差し止めとなりますので御注意ください。
各種手続きについて
加入の申込、裁定請求の手続き、住所・氏名の変更、被保険者及び受給権者の死亡などの際には各種手続きが必要です。
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町農業委員会事務局
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
メールフォームによるお問い合わせ
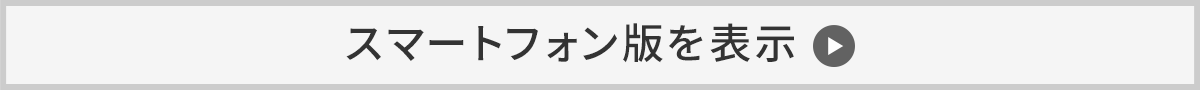












更新日:2022年11月29日