立候補を目指す方
立候補に関する手続きの流れ
町の選挙における立候補に関する手続きの流れについては以下のとおりです。なお、具体的な日程についてはそれぞれの選挙で異なりますのでご注意ください。
| 主な行事等 | 期日(選挙ごと異なる) | 備考 |
| 立候補予定者説明会 | 告示日の約1ヶ月前程度 | |
| 届出書類等事前審査及び合同個人演説説明会 | 告示日の約1周間前程度 | 立候補届出書類、選挙運動ポスター、選挙広報等の事前審査 |
| 選挙期日の告示(告示日) | 投票日の5日前まで | |
| 立候補届出受付 | 告示日の午前8時30分から午後5時まで | 受付場所は選挙ごと選挙管理委員会が定める |
| 選挙運動初日 | 立候補届出が受理されたときから | |
| 選挙公報掲載順序くじ | 告示日の午後5時以降 | |
| 期日前・不在者投票期間 | 告示日の翌日から投票日の前日まで | 午前8時30分から午後8時まで |
| 選挙運動最終日 | 投票日の前日まで | |
| 投票日 | 選挙種別(及び選挙事由(任期満了・議会の解散・補欠選挙等))ごとに選挙管理委員会が定める日 |
午前7時から午後8時(一部の投票所では午後7時まで) |
立候補するための条件
公職選挙法は、立候補の届出をした者でなければ当選人となることができないとする立候補制度をとっています。
被選挙権
被選挙権として、次の条件を備えている必要があります。
| 選挙の種類 | 条件 |
| 飯島町長選挙 |
|
| 飯島町議会議員 |
|
立候補できない方
以下の者は被選挙権を有しないため立候補が禁止されています。
- 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
供託
立候補の届出をする場合、全ての選挙において候補者ごとに一定額を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
供託は、当選する意思のない人が売名などの理由で立候補することを防ぐための制度です。その候補者の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合は、供託されたお金は全額没収されます。
| 選挙の種類 | 供託金額 | 供託物が没収される得票数、又はその没収額 |
| 飯島町長選挙 | 50万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 飯島町議会議員選挙 | 15万円 | 有効投票総数÷議員定数(12)×1/10未満 |
(注意)立候補者の届出の場合は本人が供託し、推薦届出の場合は推薦届出人が供託することとなります。
立候補の届出
選挙に立候補するには選挙長に対し「立候補の届出」が必要です。使者が届出に来ることはできますが、郵便による届出はできません。
また、届出には立候補者本人が届出を行う「本人届出」と立候補者の推薦者が届出を行う「推薦届出」があり、それぞれ届け出る書類等が異なります。
詳細は、各選挙の立候補予定者事前説明会等でお知らせいたします。
候補者の氏名について
候補者の氏名は、戸籍簿に記載されている氏名を記載しなければなりません。
ただし、次の場合には、戸籍簿に記載された氏名により記載したものとして取り扱われます。
1 .対応する常用漢字等に更正する場合
戸籍簿に記載された氏名に用いられている漢字のうち、常用漢字表に掲げる通用字体又は人名漢字表に掲げる字体(以下合せて「通用字体」という。)と異なる字体によって記載されているものがある場合に、その対応する通用字体又は通用字体に準じて整理した字体に更正して記載する場合。
(例)澤→沢、廣→広、榮→栄、瀧→滝
2. 誤字・俗字を正字に更正する場合
戸籍簿に記載された氏名が誤字・俗字である場合に、これを正字に更正して記載する場合。
(例)嶋→島、冨→富、嵜→崎
3 .変体がなをひらがなに更正する場合
戸籍簿に記載された氏名が変体がなである場合に、これをひらがなに更正して記載する場合。
(例)ゑ→え、ゐ→い
4 .旧かなづかいを現代かなづかいに更正する場合
戸籍簿に記載された氏名が旧かなづかいである場合に、これを現代かなづかいに更正して記載する場合。
(例)カナヘ→カナエ、けふ子→きょう子
通称の使用について
戸籍簿に記載された氏名以外の呼称を有しており、それが戸籍簿に記載された氏名の代わりに広く通用している場合には、選挙長の認定を受けたうえ、戸籍簿に記載された氏名に代えて、通称を使用することができます。
この場合には、立候補の届出と同時に、通称認定申請書の提出が必要です。
(注意)
-
立候補の届出後、別に通称認定申請書を提出されましても受理できません。
-
通称使用の申請者は候補者に限られます。推薦届出の場合にも通称使用申請は候補者が行うことになります。
-
通称認定申請の際には、その通称が戸籍簿に記載された氏名に代わるものとして、広く通用しているかどうかを証する資料(公の機関の発行した書類、送達された手紙又ははがき等の信書、著書等、その実績を示すもの等)の提出及び説明が必要です。
-
通称認定申請書を提出し、選挙長から認定書を交付された場合は戸籍簿に記載された氏名の文字は使用されません。なお、通称使用の認定がなされ、公に告示された後は撤回できません。
立候補の届出期間
立候補の届出期間は、選挙の期日の公示又は告示日の1日間のみとなりますのでご注意ください。
また、受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
受付場所については選挙ごと選挙管理委員会よりお知らせいたします。
立候補の辞退
一度立候補した後に候補者をやめる場合には、立候補の届出日(告示日の午後5時まで)に選挙長へ候補者辞退届を提出しなければなりません。
選挙運動について
立候補を決意したら、直ちに選挙運動に着手したいものですが、公職選挙法では、選挙運動は立候補の届出があった日からでなければすることができないとされており、事前運動は禁止されています。
事前運動として禁止されるのは、立候補の届出前における一切の選挙運動であり、買収や戸別訪問のような選挙運動期間中も禁止される行為はもちろんのこと、個々面接や電話による選挙運動のような選挙運動期間中ならできる行為であっても、これを届出前に行えば事前運動となります。
具体的にある行為が選挙運動に当たるか否かについては、個別具体の事実、状況等に即して判断されることとなります。
選挙運動について
公職選挙法において、「選挙運動」は次のとおりとされています。
| 選挙運動 | |
| 意味 | 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為 |
| 規制概要 | 選挙運動期間中に限り行うことができ、様々な規制がある。 |
選挙期間前は、「選挙運動」を行うことは一切できません(事前運動の禁止)。
なお、選挙運動と区別される立候補届出前の準備行為は行うことができます。それは、おおむね次のようなものです。
- 政党の公認を求める行為、瀬踏行為、選考会、推薦会の開催行為
- 選挙事務所借入れの内交渉
- 出納責任者又は選挙運動員就任の内交渉
- 労務者の雇入れの内交渉
- 演説会場借入れの内交渉
- 選挙演説を依頼するための内交渉
- 選挙運動用葉書による推せん依頼の内交渉
- 自動車、拡声機の借入れ交渉
- 立札、看板、ポスター等をあらかじめ作ること
- 選挙運動用資金の調達
- 候補者となろうとする者の戸籍簿の謄本又は抄本を取り寄せておくこと
(注意)ただし、これらの行為があわせて投票獲得の意図をもって行われるときは事前運動となります。
選挙運動の規制
選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、選挙運動を無制限に認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあることから、選挙の公正・公平を確保するために、様々なルール(規制)が設けられています。
- 1.選挙運動の期間に関する規制
- 選挙運動ができる期間は、立候補届が受理されたときから、選挙期日の前日までです。また、選挙当日(投票日)の選挙運動が禁止されていることにも注意が必要です。
- 2.選挙運動の主体に関する規制
- 選挙運動は原則として誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。
-
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、警察官など)
- 年齢満18歳未満の者
- 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
- 3.選挙運動の方法に関する規制
- 選挙運動に使用できる文書図画(ビラ、ポスター、新聞広告、インターネットなど)は制限されており、それぞれ規格や数量、使用方法などの規制があります。また、個人(合同)演説会や街頭演説についても、開催主体や実施方法などについて規制があります。
- このほか、署名運動の禁止、戸別訪問の禁止や飲食物の提供の禁止などの規制があります。
- 4.選挙運動の費用に関する規制と選挙公営
- お金のかからない選挙となるよう、選挙運動費用の支出に最高限度額が設けられています。
(注意)選挙運動規制は、多岐にわたっているほか、選挙ごとに異なっています。詳細は選挙管理委員会へお問合せください。
選挙運動に係る公営(公費負担)制度について
概要
お金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等等のため、候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する選挙公営制度があります。
町の選挙において、候補者の選挙運動に係る費用を「飯島町議会議員及び飯島町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例」の規定に基づき、予め業者と契約を締結し、届け出ることでその一部を公費で負担することができます。
ただし、候補者が供託物を没収された場合には公費負担を請求することができませんのでご留意ください。
公費負担の対象とその限度額

詳しくは、立候補予定者事前説明会等において説明いたしますが、ご不明な点は選挙管理委員会へお問合せください。
その他の公営制度
1.選挙運動用通常葉書の交付
選挙運動に使用する選挙運動用通常葉書は、定められた枚数まで無料で差し出すことができます。
なお、手続きについては立候補予定者事前説明会等でお知らせいたします。
| 選挙種別 | 限度枚数 |
| 町長選挙 | 2,500枚 |
| 町議会議員選挙 | 800枚 |
2.ポスター掲示場の設置
(注意)選挙管理委員会は、掲示場の設置のみを行います。
3.選挙公報の発行
(注意)選挙管理委員会は、掲載順の決定(くじ)、印刷及び配布のみを行います。原稿作成時の注意事項等は立候補予定者事前説明会等で説明いたします。
4.投票所における候補者氏名掲示の作成
(参考:総務省ホームページ)
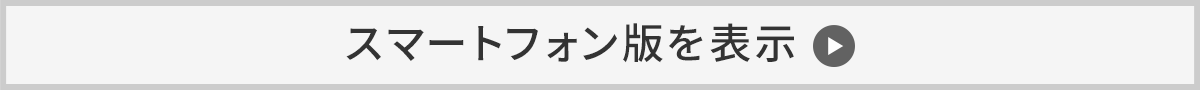












更新日:2024年10月31日