個人住民税
町県民税(個人住民税)
町県民税は、様々な行政サービスの提供に必要となる費用を、広く町民の皆さんに、その能力に応じて負担していただく税金です。町県民税の税額は、前年中(1月1日〜12月31日)の所得をもとに算出され、原則として毎年1月1日(賦課期日)の住所地で課税されます。

町県民税の一年間のながれ
町県民税がかかる方(納税義務者)
- 町内に住所がある方:均等割、所得割
- 町内に住所はないが、町内に事務所、事業所、家屋敷(いえやしき)がある方:均等割
(注意)町内に住所があるか、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
- 事務所、事業所とは事業を行うための施設であり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。自己の所有であるかどうかは問いません。
- 家屋敷とは、自己又は家族が居住するために住所地以外に設けた独立性のある住宅をいいます。常に居住できる状態にあるものであれば、現に居住しているかどうかを問いません。(別荘、別宅、マンション、アパートなどが該当します。)
町県民税がかからない方
均等割や所得割がかからない方
- 生活保護法により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(扶養者の数+1)+10万円+16万8千円
(注意)16万8千円は扶養者がいる場合に加算されます。
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が次の金額以下の方
35万円×(扶養者の数+1)+10万円+32万円
(注意)32万円は扶養者がいる場合に加算されます。
町県民税の内訳
均等割
一定以上所得がある方に一律定額を負担していただくものです。
年額 5,500円 (町民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円)
所得割
前年の所得や控除により次の式で算出します。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
納税の方法
納税者の所得状況に応じて、次のいずれかの方法又は普通徴収と特別徴収を組み合わせて納税していただきます。
普通徴収
給与からの特別徴収がされない給与所得者、年金所得者、事業所得者などの町県民税は、納税通知書により納税者本人へ通知され、6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納めていただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者は、町から会社等(給与支払者)を通じて特別徴収税額通知書により課税内容が通知され、会社等が毎年6月から翌年の5月まで、給与を支払う際に給与から町県民税を天引きして納めていただきます。
所得税を源泉徴収している事業者は、地方税法第321条の4及び町税条例第45条の規定により、特別徴収が義務付けられています。
公的年金からの特別徴収
厚生年金や共済年金など公的年金を受給されている65歳以上の方の町県民税は、年6回の年金給付の際に税額を天引きして納めていただきます。
令和6年度から国の森林環境税の課税が始まります。
平成26年度から、1人に対し年額1,000円ご負担いただいている東日本大震災に発生に伴う「復興特別税」が令和5年度で終了します。
代わって令和6年度からは、新たに同額の1人1,000円の『森林環境税』の課税が開始されます。
(町県民税均等割均等割の表)

森林環境税の非課税
町県民税の非課税要件と同様に、町県民税均等割を納付いただかない方は非課税になる予定です。詳しい要件は、「町県民税がかからない方」の欄をご覧ください。
森林環境税とは?
パリ協定に伴い、国の温室効果ガス排出削減の目達成や、災害の防止を図るため、森林整備に必要な地方税源を安定的に確保する目的として創設されました。
税金の使い道は?
森林環境税の収入に相当する額は、都道府県と市町村に『森林環境譲与税』という名目で、森林整備等の費用として配分されます。譲与税はすでに令和元年度より飯島町にも配分があり、様々な森林環境整備のために活用されています。例として、令和2年度に飯島町産のひのきを用いた鉛筆を作成し、町内小学校の新入生に配布する事業を行いました。
令和6年から特別徴収税額の受け取り方法が電子データとして受け取れます
特別徴収の方法が下記の通り変更となります
(事業者用)
| 受け取り方法(どちらかを選択) | 詳細 |
| 電子データ(eLTAX) | eLTAXで受け取り |
| 書面 | 郵送で受け取り |
(従業員用)
| 受け取り方法(どちらかを選択) | 詳細 |
| 電子データ(eLTAX) | eLTAXで受け取り |
| 書面 | 郵送で受け取り |
電子データで受け取りを希望される場合はeLTAX(エルタックス)での給与支払報告書の提出が必要です。eLTAXでの給与支払報告書提出時、受け取り方法を選択してください
事業主様へ 町県民税の特別徴収をお願いします
町県民税は、より豊かで住みよい地域をつくるための重要な税源の一つですが、未収金(市町村・県民税の未収金額)が累積しています。
未収金の発生要因のひとつである納税者の納め忘れを未然に防ぐため、給与からの天引き(特別徴収)について、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。
特別徴収のメリット
- 事業所においては、所得税のように個別の税額計算や年末調整事務がありませんので、事業者の皆様の過度な事務負担は生じません。
- 従業員が常時10人未満の事業所は、年12回の納期を年2回にする特例制度があります。
事前の申請が必要になります。 - 従業員にとっては、納税のために金融機関等に出向く手間もなくなり、うっかり納め忘れることがなくなります。
- 自分で金融機関等に出向いて納める「普通徴収」は年4回払いですが、「特別徴収」は年12回に分割して給与天引きされるため、1回当たりの負担額が少なくなります。
令和8年度から適用される税制改正について
国の税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
この改正は令和7年1月1日から12月31までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの給与収入額が190万円以下の方の控除額が、令和8年度の個人住民税から最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
改正前と改正後の比較
|
給与収入金額
|
改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万以下 | 給与等の収入金額×40%ー10万円 | 65万円 | 10万円〜3万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 | 3万円〜0円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 0万円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
0万円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし | 0万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
0万円 |
留意事項
給与収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方に対する改正はありません。
2 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
対象及び改正内容
改正前と改正後の比較
|
所得要件 |
改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に参入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(特定扶養親族)がいる場合、その納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
合計所得金額が58万円超123万円以下
控除対象扶養親族に該当しない
控除額
|
扶養親族の合計所得金額 |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 58万円超95万以下 |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
4 その他
基礎控除の見直しは所得税のみ行われます。個人住民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。
町県民税の申告について
申告期間
所得税の確定申告と同期間になります。(例年2月16日~3月15日頃)
申告が必要な方には、2月初旬に申告書をお送りします。町県民税の申告は下記を参考にしていただき、必ず期間内に申告してください。
なお、申告の内容(確定申告、確定申告分離分を含む)は国民健康保険税算出の資料にもなります。
町県民税の申告が必要ない方
- 税務署へ確定申告をする方
- 給与収入が1か所のみで、年末調整をし、給与収入以外の収入がない方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く)の収入のみで、その他に収入がない方
(扶養控除や所得控除を受けようとする場合は申告をしてください。) - 収入がなく町内に住所がある方の扶養親族となっている方
(町外に住所がある方の扶養親族になっている場合は、その旨の申告をお願いします。)
上記に該当しない方で申告が必要な方
- 営業等・農業・不動産・配当・雑・一時・譲渡等の収入がある方で、確定申告書の提出を要しない方
(注意)個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方は基調と帳簿書類の保存が必要です。 - 給与所得者(パート・アルバイト等の収入を含む)で
- 給与以外の所得が20万円以下の方
- 2か所以上の事業所から給与を受けている方
- 年の途中で就職、退職した方で年末調整をしていない方
- 前年中に収入がなかった方や、町外に住所がある方の扶養親族になっている方
- 非課税収入(遺族年金、障害年金等)のみの方で、誰の扶養にもなっていない方
- (注意1)申告が必要な方が申告をしない場合、所得証明等が発行できず、行政サービスに影響がでる場合があります。
- (注意2)公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ、その全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要になりますが、町県民税申告は必要になります。
申告が必要ない方でも配偶者控除や扶養控除が正しく反映されているか確認をしてください。 - (注意3)医療費控除を受ける方や繰越損失の控除を受ける方は申告が必要になります。
各月の収入と支出の状況表 (PDFファイル: 179.0KB)
セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 82.9KB)
寄附金に関する控除について
ふるさと納税
ワンストップ特例について
ふるさと納税をしていただくと、確定申告が不要になるワンストップ特例があります。一定の条件がありますので、詳しくはワンストップ特例注意事項をご確認ください。
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
次の基本控除額と特例控除額の合計額が控除されます。複数の都道府県、市区町村に対して寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。
- 基本控除額 (寄附金の合計額(総所得金額等の30%を限度)−2千円)×10%
- 特例控除額 (個人住民税所得割の10%を限度)
(寄附金の合計額(寄附金の合計額に限度適用はありません。)−2千円)×(90%−寄附者の所得税の税率)
ワンストップ特例を申請するみなさまへ (PDFファイル: 120.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
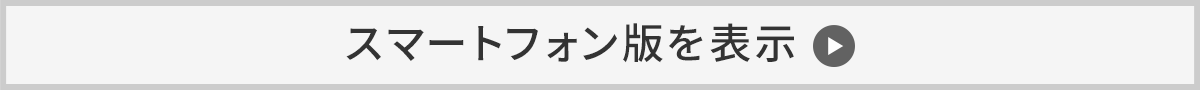












更新日:2025年11月04日