予防接種(子ども)

「予防接種」とは、疾病の予防に有効であると確認されているワクチンを接種して、免疫(病気に対する抵抗力)をつくることにより、発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。
お母さんから赤ちゃんに渡される病気に対する抵抗力(免疫)は生後数ヵ月の間に自然と失われていくため、赤ちゃん自身で免疫を作る必要が生じてきます。また、子どもの発育とともに外出する機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。
予防接種に対する正しい理解の下で、予防接種を受けるようにしましょう。
予防接種法が定める予防接種
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた定期接種と、それ以外の任意接種があります。
定期接種
定期接種の対象疾病は以下の2つに分類され、それぞれの疾病に対し予防接種が行われます。予防接種法により決められた期間に、公費で接種を受けることができます。(期間外は自己負担となります。またB類疾病の予防接種は、自己負担があります。)
A類疾病(集団予防に重点、努力義務あり)
- ロタウイルス感染症
- B型肝炎
- 小児の肺炎球菌感染症
- ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・Hib感染症
- 結核(BCG)
- 麻しん・風しん
- 水痘(みずぼうそう)
- 日本脳炎
- ヒトパピローマーウイルス感染症
B類疾病(個人予防に重点、努力義務なし)
- 季節性インフルエンザ
- 高齢者の肺炎球菌感染症
- 新型コロナウイルス感染症
- 帯状疱疹
任意接種
おたふくかぜ、インフルエンザなどがあり、希望者が費用を自己負担をして接種を受けます。接種の際はかかりつけ医と相談のうえ受けてください。
なお、飯島町では住民のみなさんの健康増進を目的に、以下の任意予防接種の費用助成を行っています。
風しん予防接種
風しんによる「先天性風しん症候群」予防を目的とし、成人を対象とします。詳しくは、飯島町風しん予防接種費用助成事業をごらんください。
おたふくかぜ予防接種
飯島町に住所を有する1歳から3歳未満の児を対象とします。詳しくは、おたふくかぜワクチン任意予防接種費用助成事業をごらんください。
中学3年生インフルエンザ予防接種
受験を控えた中学3年生を対象とします。対象となる方には予診票と通知を郵送します。
予防接種法により行う予防接種
すべての定期予防接種は協力医療機関での個別接種です。協力医療機関を予約のうえ、接種を受けてください。なお、予防接種の対象となる方には、通知・予診票などを郵送しますので、ご確認ください。
予防接種を受ける前に注意したいこと
- 接種当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったところがないことを確認するようにしましょう。体調に変化がある場合は、かかりつけ医に相談の上、接種をどうするか判断するようにしましょう。
- 受ける予定の予防接種について、町からの通知や説明をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは、接種を受ける前に接種医へ質問しましょう。
- 母子手帳は予防接種の大切な記録を記入します。必ず持っていきましょう。
- 予診票は、お子さんを診察して接種する医師への大切な情報です。正確に記入しましょう。
- 予防接種を受けるお子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者の方が連れて行きましょう。
予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない方
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害など基礎疾患のある方
- 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状のみられたかた方
- 過去にけいれん(ひきつけ)をおこしたことがある方
- 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある方もしくは近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分に対してアレルギーをおこすおそれのある方
予防接種後を受けることができない方
- 明らかに発熱している方(通常は37.5℃を超える場合)
- 重い急性疾患にかかっている方
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分でアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性じんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと)をおこしたことがある方
- 予防接種の対象者で妊娠していることが明らかな人
- BCG接種の場合においては、外傷などによるケロイドが認められるお子さん
- その他、かかりつけ医師に予防接種を受けないほうがいいといわれた方
予防接種後の注意
- 接種後30分間程度は、ショックやアナフィラキシーがおこることがありますので、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。
- 接種後、生ワクチンで4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴の問題はありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 当日は、はげしい運動は避けましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
接種間隔を守りましょう!
異なった種類のワクチンを接種する場合には間隔ことを守ることが必要です。
適正な接種間隔でないものは、予防接種法に基づかない法定外の接種とみなし、自己負担となります。また、接種による健康被害の救済措置の対象となりません。
なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔があるので、間違えないようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 健康福祉課 保健医療係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
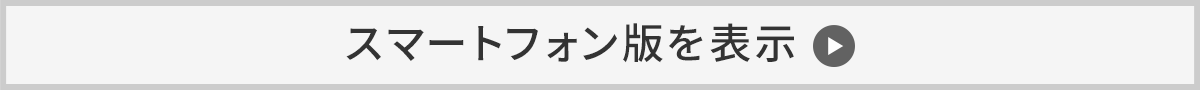












更新日:2025年04月01日