認定外道路(赤線)
認定外道路とは
認定外道路とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道のような道路法の適用を受ける道路以外のもので、法定外道路ともいいます。
法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれることもあります。
自営工事・占用許可の手続きについて
認定外道路内で、自営工事・占用許可に該当する行為を行うときは、町の許可が必要になりますので、不明な点は事前にご相談いただき、必ず許可を得てから着手するようにしてください。
ご近所で、事前の周知もなく、認定外道路で工事等を見かけた場合は、町へご連絡をお願いします。(通報者が特定されないよう秘密を守ります。)
1.自営工事
認定外道路を敷地の占用を伴わないで工事を行う場合は、事前に町長の許可を受ける必要があります。
なお、許可までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに承認申請書をご提出ください。
自営工事の例
- ガードレールや縁石を除去して出入り口として使用したい
- 側溝を入替・新設したい
- 法面を埋め立てたり、舗装をしたい
- ガードパイプの新設・撤去を行いたい
自営工事手続の主な流れ
1.自営工事承認申請書を提出(申請者)(注)1週間前までに
2.現地確認(町)
(注)境界杭等を動かす必要があるなど、場合によって申請者、関係者の立会が必要です。
3.許可書の交付(町)
4.工事箇所自治会等へ工事の周知(申請者)
5.自営工事着手届の提出(申請者)
6.自営工事完了届の提出(申請者)
7.現地確認(申請者・町)
(注)境界杭等を動かす必要があるなど、場合によって申請者、関係者の立会が必要です。
申請に必要な書類
申請書に以下の書類を添付して提出してください。
1.位置図(5万分の1以上)
2.平面図(600分の1以上)
3.縦横断図(600分の1以上)
4.構造詳細図(600分の1以上)
5.公図写
6.設計書及び仕様書(小規模工事は除く)
7.三斜丈量図(面積計算図)
8.工事設計書
9.現場写真
10.地元区長の意見書、地元自治会長の同意書及び隣接土地所有者の同意書
※特に自治会長の同意書を作成する際は、周辺住民の理解が得られている
ことを説明してください。
11.帰属承諾書
同意書(隣接土地所有者) (Wordファイル: 33.5KB)
2.占用
道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路を継続して使用し占用する場合には、町長の許可を受ける必要があります。
なお、許可までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに許可申請書をご提出ください。
また、占用の地位承継や権利譲渡、占用を終了する場合は、書類の提出が必要です。
占用の例
- 看板や電柱を設置したい
- 地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設したい
- 側溝にグレーチングや蓋をして出入り口として使用したい
- 法面を埋めたり削って出入り口として使用したい
占用手続の主な流れ
上記の「自営工事手続の主な流れ」と同様です。
申請に必要な書類
申請書に以下の書類を添付して提出してください。
1.位置図
2.公図写
3.実測平面図及び実測縦横断面図
4.面積計算書
5.工作物設置又は土地の形状変更にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した図面
6.許可の申請のかかる行為については、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面、又は受ける見込に関する書面
7.許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書
8.その他町長が必要とする図書
占用料等免除(減額)申請書 (Wordファイル: 30.0KB)
飯島町公共物管理条例施行規則(別ウインドウで外部サイトが開きます)
◆過去の事例◆[無許可で工事着手]
(内容)
所有する敷地と接する赤線を合わせて舗装工事を実施する際に、公図等で状況を確認しなかったため、認定外道路(以下「赤線」という)まで含めて工事に着手した。
周辺住民から、赤線を含み工事していると指摘されたため、工事の請負業者は役場で「公共物管理条例」に基づく許可申請書類を受け取り、許可後でなければ工事は着手できないと説明を受けたにもかかわらず工事を継続した。
工事が継続しているため、再度、住民から町へ通報があり、町は現場で工事中止を伝えたが工事は継続した。こうした請負業者の対応や無許可の状態、周辺住民の同意も得られていない状況から、町は原状回復(元の状態に戻すこと)をさせることとなった。
なお、原状回復の指示をしてから完了するまで、町・施主・請負業者間のやりとりに時間がかかったことや、町の対応にも不備があったことにより数ヶ月を要してしまい、周辺住民の皆さんにご迷惑をおかけする結果となった。
【事例検証】町対応の課題
・町が赤線工事に係る手続きについて、住民・業者に対し十分周知ができていなかったこと。
・工事請負業者に工事の中止を伝えたが止められず、施主に中止の旨を伝えなかったこと。
・住民から通報を受けた当日に現場確認を実施しなかったこと。(実施していれば、1日でも早く工事を止められた可能性があったこと)
・原状回復工事の完了報告後、町が事前に現場確認を実施しなかったため、関係者との立ち合い時に指示どおりの内容で施工されていないことが判明したこと、また、関係者全員出席のうえで立ち合いを実施しなかったことにより、改めて実施することになってしまったこと。
【事例検証】町の改善方針
・許可手続きの方法を町ホームページへ掲載することや、区長自治会長会等で周知します。
・許可申請書を受け取りに来た施主又は工事業者に対しては、許可後の着手を徹底します。
・工事中止を指示する際には、請負業者のほか施主にも必ず指示を行います。
・工事着手から完了まで、定期的な現場確認を実施し、問題等があれば施主又は請負業者に指示等を行います。
・問題や課題の発生する恐れがある案件では、周辺住民・関係者と情報共有を徹底します。
・工事完了後の立会いには、必ず関係者全員の出席を求めるとともに、計画どおりの施工を事前に確認します。
【事例検証】町の総括
今回の公共物管理条例違反の案件については、町長以下職員全員が検証結果を踏まえ、住民の皆さん及び施工業者等への周知と情報提供を徹底するとともに、職員の法令遵守及び適正で迅速な住民サービスの向上に努め、より一層の住民の皆さんに寄り添った行政運営を図ってまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 企画政策課 財政係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
メールフォームによるお問い合わせ
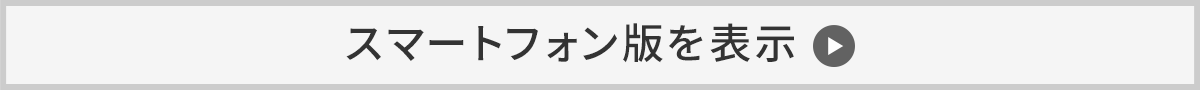












更新日:2025年03月27日